
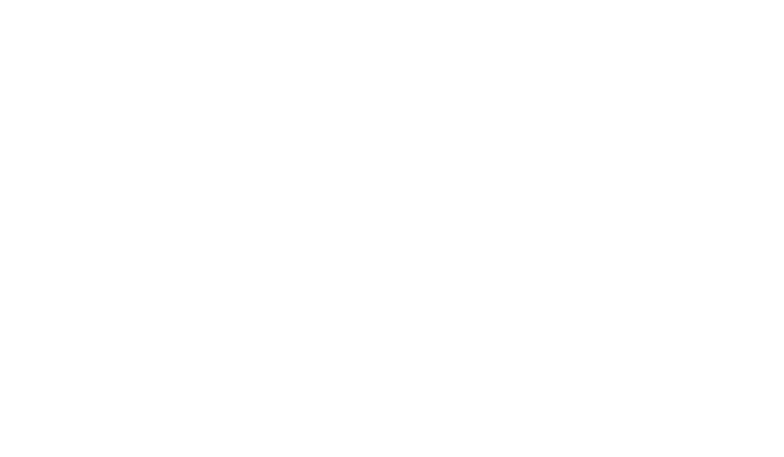
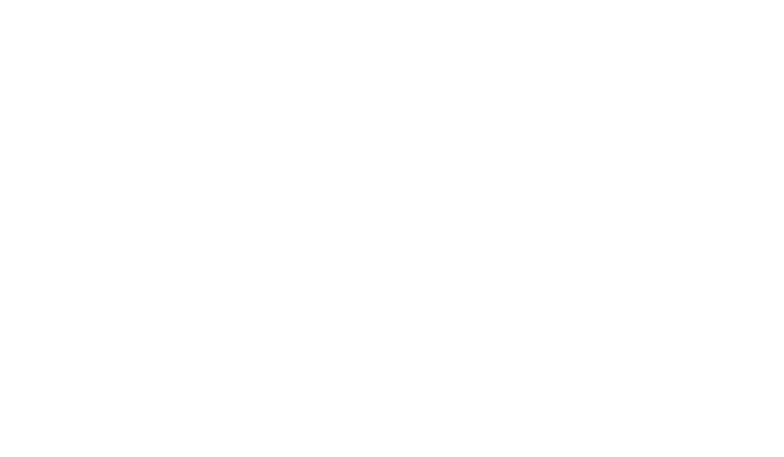
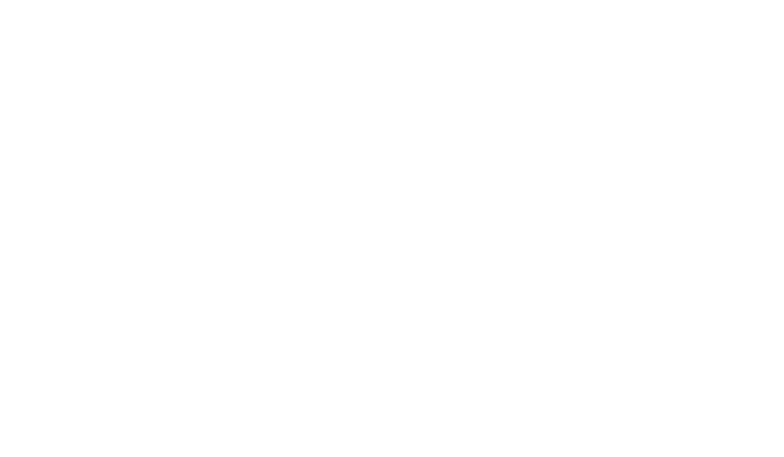
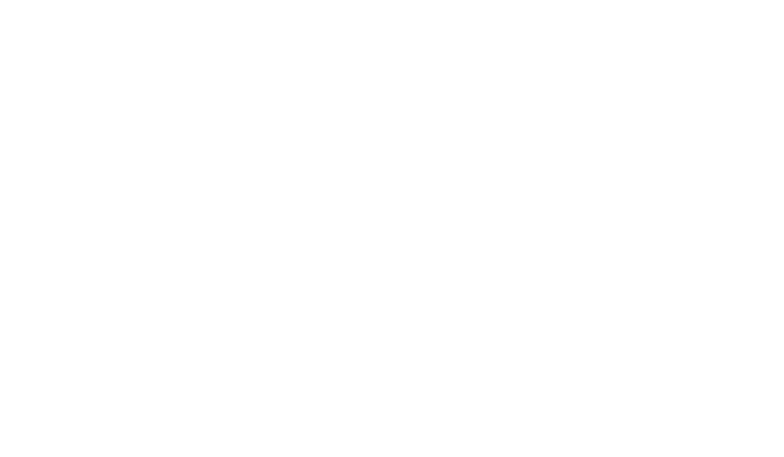
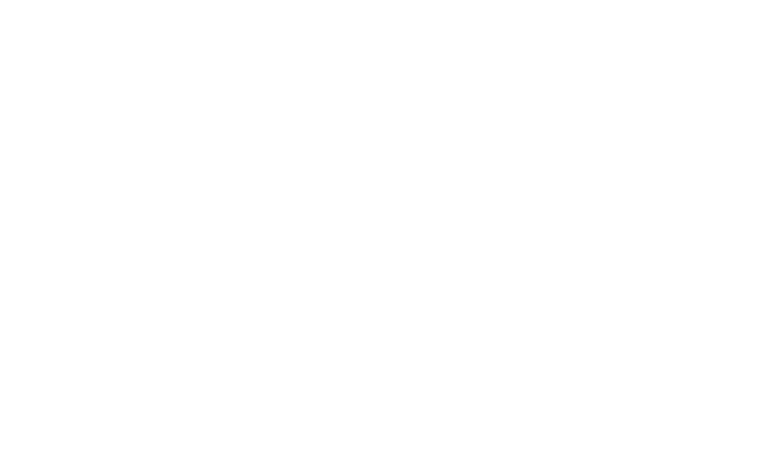
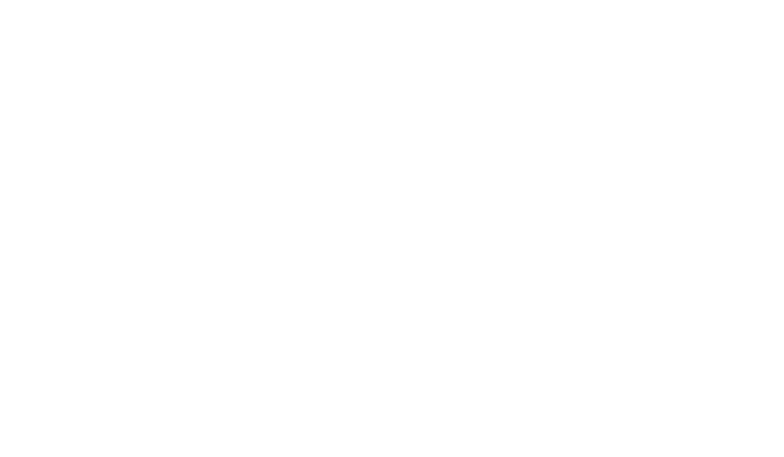
訪れる者を温かく迎え入れるというよりは、威圧するような印象さえ受ける重厚な造りの門。その奥に建てられた屋敷もやはりどっしりとして、いかにも身分の高い人間が住むに相応しい佇まいだ。
だがこの屋敷には主が無かった。住む者はもちろん、寄り付く者さえ滅多にない。おそらくこの屋敷にとって、寅次郎は久々に訪れた客人であろう。もっとも物言わぬ木造の門や屋敷が、寅次郎と言の葉を交わすことなどありはしないが。
「…………」
寅次郎が手で押すと、その見た目とは裏腹に巨大な門はいとも簡単に開いた。普通ならかけられているはずの閂も、今は腐った木屑に成り果てて門の内側に落ちている。
(たった二年だというのに、ずいぶんと荒れてしまったものですね……)
門の外側よりも、その内側に入ってから目に映る光景の方が悲惨だった。破れた障子戸、腐った畳、朽ちかけた柱。寅次郎は以前に何度かこの屋敷を訪れたことがあったが、その頃の面影は何一つ見つけられない。
(父上がご覧になられたら、さぞかし心を痛めることでしょう……)
かつてこの屋敷の主は、寅次郎の父の古い友人であった。大組――長州藩主直属の家臣として仕える由緒正しき家柄。その名に恥じぬ高潔な人物であったことを寅次郎もよく覚えている。
だがその人物はすでに亡く、藩内では名を出すことすら憚られると言う。なぜならば彼は、ある汚名を着せられた末に身分を奪われ、一族郎党を藩中枢から追放されてしまったからだ。
(……実に惜しい方を亡くしたものですね。あの方のように真にこの藩を憂う忠臣が、果たして今の長州藩にいるでしょうか?)
寅次郎は深くため息をつく。その時、草履の先に何かが当たった。
「これは……」
足元に落ちていたのは古びた人形だった。拾い上げてみると、それが見覚えのある物であると気づく。
(彼女のものですね)
脳裏に浮かんだのは、人見知りをして自らの父の背に隠れる幼い少女の姿。この屋敷の一人娘だ。
「彼女は今どこに?」
汚れた人形を手に、寅次郎はぽつりと呟いた。
数刻の後、寅次郎は小さな家屋の前に立っていた。その粗末な造りをより正確に言い表すのならば、あばら家と言ったほうが適当であろう。萩の町外れからさらに離れた場所。まるで人目を避けるように建てられたこの家屋に、あの人形の持ち主が住んでいると聞いた。
(いささか信じがたいですが……)
そう思いつつも、寅次郎は歩を進める。
「ごめんください」
反応はすぐには無かった。吹き付ける木枯らしが、寅次郎の長い髪をいたずらに弄ぶ。今日もひどく冷え込んでいた。こうして何もせずに佇んでいると、凍てつく大気がすぐさま寅次郎の体温を奪っていく。
「ごめんください、どなたかいらっしゃいますか?」
寅次郎はもう一度声をかけた。やはり反応はない。
(……間違いだったのでしょうか)
この場所を教えてくれた者には申し訳ないが、そうであればいいと寅次郎は思っていた。あまりにも寂しいこの場所に、できればあの娘の姿があってほしくはない。
(……仕方がありません。帰りましょう)
寅次郎が諦めて、踵を返した時だった。
「……どちら様でしょう?」
家の中から、今にも消え入りそうな声が聞こえた。寅次郎は足を止め、すぐさま振り返る。
「吉田寅次郎と申します」
「吉田……寅次郎様?」
「覚えていらっしゃるでしょうか? お父上の友人であった杉百合之助の次男です」
か細い声は一度途切れた。代わりに小さな足音が近づいてくる。寅次郎が今一歩足を進めると、柱に隠れるように家の中から顔を出した娘を見つけた。華やかな小紋とは程遠い薄汚れた着物を身に纏ってはいたが、その姿が寅次郎の記憶の中の少女と重なる。
「お久しぶりです。やっとお会いできましたね」
寅次郎は微笑んだ。
「っ……」
娘はぱっと目を逸らし、着物の裾を翻す。
「あ、待ってください!」
寅次郎は思わず娘の手を取っていた。荒れて冷え切った小さな手だ。
「は……離してください……!」
「……っと、失礼しました」
はっとしてすぐに手を離すと、娘は寅次郎の視線から自らの手を隠した。
「申し訳ありません。いきなり訪れておいて、不躾な真似を……」
「……いえ。私の方こそ、ご無礼をお許しください」
娘は深々と頭を下げる。粗末な格好をしていても、その所作や言葉尻から気品が感じられた。
「寅次郎様、本日はなぜこのような場所に?」
「あなたに会いに来たのですよ」
「私に……?」
「ええ、そうです」
娘は信じられないものでも見るような目で、寅次郎を見ていた。見開かれた大きな瞳には、微かに少女の頃の面影が見て取れる。
「お……お帰りください」
娘はまた寅次郎から目を逸らした。
「……ご迷惑でしたか?」
「ご迷惑をおかけしているのは……私の方です。私のような者と会っていると知られては、寅次郎様も咎めを受けるかもしれません。ですから……」
「私のためにも、早く立ち去れと?」
「……はい」
娘は俯いたまま、決して寅次郎と目を合わせようとしない。まるで手酷い虐待を受けて怯える子犬のようだと寅次郎は思う。二年という月日の中で、この娘の負った傷がそれほど深いということなのだろう。
「……ではその咎めとやらを、私は喜んで受けましょう」
「え……?」
「あなたのお父上が被られたのは無実の罪。世間が知らずとも、私はよく知っています。罪なき罪を負うあなたにも、あなたとこうして共にいる私も、元々誰にも咎められる謂れはありません。それでも咎めたい者があるのならば、あとはただ水のように静かな心で受け流せばいいだけなのです」
寅次郎は身を屈めた。娘と初めて出会った時も、同じようにした覚えがある。膝を着かずとも視線を合わせることができるのは、少女から大人へと娘の時が流れたからだろう。
「私は自らの意思でここに来ました。私があなたに会いたいと思ったからです。あなたが私の身を案じてくださることは嬉しいですが、私にとって私に投げかけられるであろう世間の言葉など取るに足らない、小さなことなのですよ。大切なのは、今こうして目の前にいるあなた自身なのです」
寅次郎は目を細めた。
「本当は様子を見るだけと思っていたのですが、少々気が変わりました。不躾を承知でお聞きします。あなたさえよければ我が家に……杉家に来ませんか?」
娘は数度瞬きを繰り返した。見開かれていた黒い瞳が、さらに一回り大きくなる。
「それは……どういう意味ですか?」
「ここを出て、私たちと共に暮らすということです」
娘は寅次郎を見つめたまま言葉を失っていた。その瞳を揺らすのは、驚きよりも困惑の色の方が強い。今この場で返事を求めるのは、酷というものだろう。そう理解して、寅次郎は静かに身を起こした。
「……五日後、あなたを迎えに参ります。心が決まったら私と共に来てください。もしもあなたが拒まれるのなら、もちろん無理強いはしません。関わるなとおっしゃるなら、二度とあなたの前に現れないと誓いましょう」
寅次郎はそっと手を伸ばし、娘の頭を撫でた。これもまた、出会った時の記憶と重なる。
「だからどうか、よく考えておいてください。私はあなたを待っています」
長い長い沈黙の後、娘はこくりと頷いた。寅次郎はふっと唇を綻ばせる。
「それではまた、五日後に」
豊かな黒髪をなびかせ、寅次郎が踵を返す。その姿が見えなくなるまで、娘はただ静かに寅次郎を見つめていた。










