
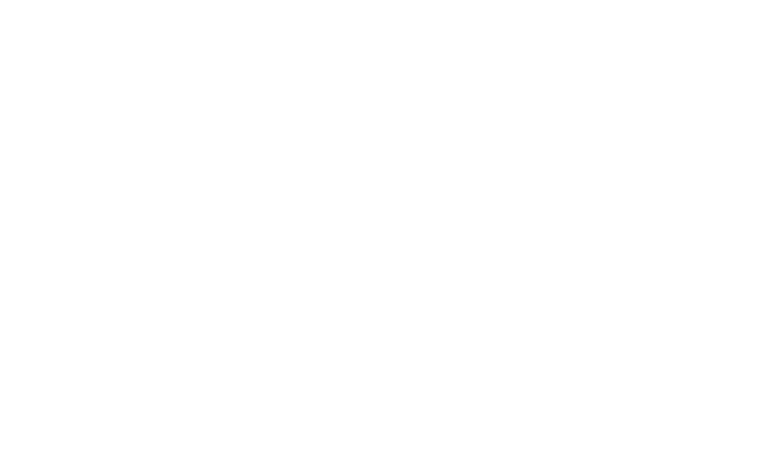
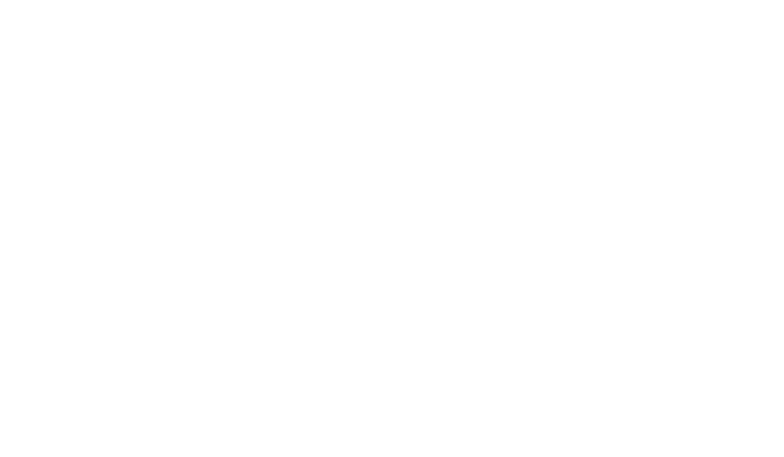
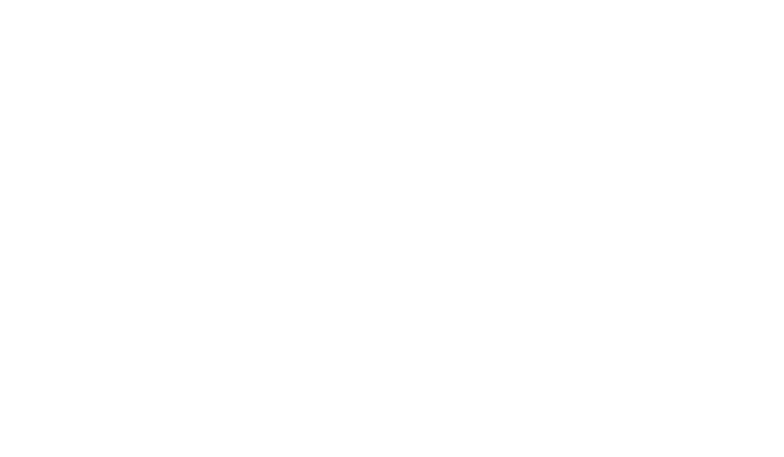
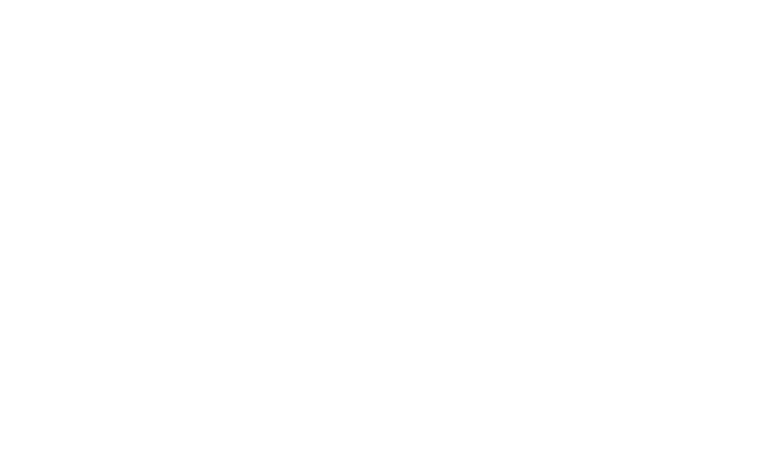
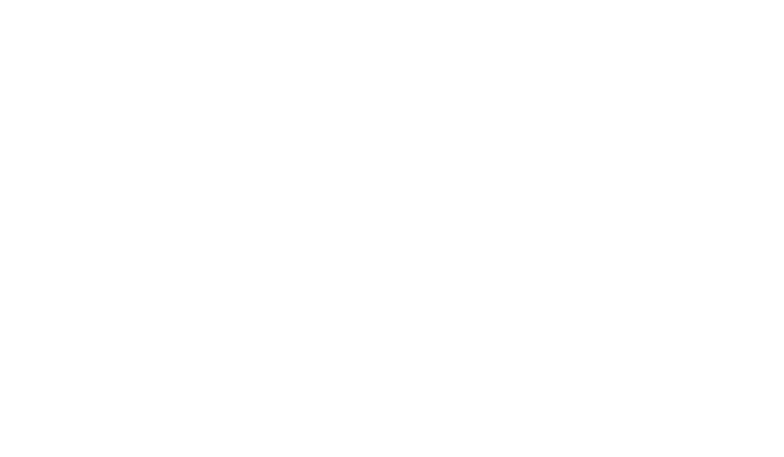
「はっ!」
気迫を込めた鋭い声と共に一際大きく踏み込むと、仮想の敵を真っ向から斬り下ろした白刃が地面と平行にぴたりと動きを止める。
「っ……はぁ……」
久坂の息はひどく乱れていた。渇いた喉の奥がひりつき、喘ぐように大きく肩を上下させる。
(すっかり鈍ってしまったな)
薄い唇を自嘲の形に歪めて、着物の袖でぐっと額を拭う。まだ雪解けから間もない如月の頃だというのに、身体中から玉のような汗が噴き出ていた。
(最後にこれを握ったのはいつだったか……)
細めた双眸が映すのは、手中にある一振りの刀。間違いなく人を殺めるために作られたものだが、鍛えられた鋼の刃は未だ一滴の血も知らない。今は亡き兄の玄機が、かつて腰に帯びていたものだ。
(子供ながらに憧れたこともあったが、まさか本当に俺がこうして振るう日がくるとはな)
くっと喉を鳴らしてから顔を上げ、空を仰ぐ。冬から春へと季節が移ろう時期特有の澄んだ空気は、鍛錬で火照った肌に心地良い。
しばしの間その場で身を憩わせると、静かに刀を納めた。だが一度離れた指先は、すぐにまた刀の柄へと戻される。門の方に人の気配を感じた。来客の予定はない。
「……誰だ?」
肩越しに振り返ると同時に、左手で鯉口を切る。視線の先から姿を現した相手が少しでも不審な動きを見せれば、すぐさま抜刀できるよう身構えていたのだが――。
「わ……私……」
誰何の声に応えたのは、思いの外か細い声だった。途端に久坂の緊張は霧散し、その唇からは短い嘆息が零れ落ちる。
「最初から一声かければいいだろう。一歩間違えたら斬り捨てていたところだ」
今度こそ本当に刀から手を離し、久坂は門の方へ歩み寄る。植え込みの陰に佇んでいたのは、久坂もよく知る娘だった。
「ごめんなさい。まさか剣の稽古をしてるなんて思わなくて」
「……まあ、そうだろうな」
医者の身で帯刀を許されているというのも、よく考えれば妙な話だ。
「ところで今日はどうした? まさか具合でも悪いのか?」
「ううん。ご近所さんから根菜をたくさん戴いたから、お母さんと煮物にしたの。そのお裾分けに」
娘はそう言って、抱えていた風呂敷包みを解いてみせる。重箱のふたを開けると、煮汁の染みた大根や芋がびっしりと詰められていた。
「本当にたくさんだな」
「うちじゃ食べきれなくて……」
「そうか、助かる。いつもすまないな」
久坂は微かに口元を綻ばせると、風呂敷ごと重箱を受け取る。その様子に娘もほっとしたようだったが、急に目を逸らしてしまった。よく見ればその頬が仄かに朱を帯びている。久坂は訝しげに眉を寄せたが、すぐにその理由に行き着いた。
激しい鍛錬を重ねるうちに、首から胸元にかけて自身の着物がひどく着崩れてしまっている。
(こいつは箱入りだったな)
家柄が良いというわけでもないが、病弱に生まれついたために今までの人生の大半を家の中で過ごしてきたこの娘にとって、肌蹴た男の胸など見慣れないものだろう。
「見苦しいところを見せた」
気づかなかったのは自分の落ち度だと、久坂はすぐさま襟を正す。娘はまだ少し目のやり場に困りながら、首を横に振るった。
「稽古のお邪魔よね。私はこれで……」
「いや、待て」
足早に立ち去ろうとする娘を、久坂の声が引き留める。
「ちょうど終わりにしようと思っていた。せっかく来たのだから、少しゆっくりして行け。このあばら家に来る客人も貴重だからな。茶の一つも淹れさせろ」
娘の返事は待たずに踵を返した久坂は、茶の用意をしにさっさと家に入ってしまった。
湯呑みを二つ載せた盆を手に久坂が戻ると、娘は縁側に腰を下ろして畳敷きの室内を見つめていた。
「何か気になるか?」
娘の隣に腰を下ろすと、久坂は持ってきた湯呑みの一つを差し出す。
「どこか旅にでも出るの?」
湯呑みを受け取りながら、娘は再び室内へと顔を向ける。その視線の先には箱枕や提灯、ろうそくなど旅の道具が一まとめに置かれていた。
「ああ、まだ言っていなかったな。九州遊学を許された。もうしばらくしたら萩を出る」
自ら淹れた茶を啜りながら久坂は言う。
「それで剣の稽古を?」
「まあな」
湯呑みを置くと、久坂は腰の刀に触れた。
「不作がもたらした貧困に耐えかねて野盗に身を落とす者もいれば、藩を脱した浪士達が徒党を組んで乱暴を働いている村もあると言う。この辺りは平和そのものだが、萩から一歩外に出れば世の中はかつてないほど乱れている。そんな時勢だ。道中自分の身一つ守れないようでは話にならないだろう」
「そうね……」
娘が表情を曇らせる。聞かずとも、何を思っているのかは見て取れた。
(言葉が足りなかったか……)
「心配するな」
刀から離した指先を伸ばし、久坂は不器用な手つきで娘の頭をそっと撫でる。驚いて顔を上げた娘と視線が交錯すると、その瞳の奥を覗き込むように顔を寄せた。
「あくまで勉学のための旅だからな。いらんいざこざに巻き込まれるのは俺とて御免だ。面倒事はできうる限り避けて行く」
言い聞かせるように言葉を紡ぐと、久坂は柔らかく笑んで見せた
「刀を抜く機会など無いほうがいい。……そうだろう?」
「うん……」
娘が頷くと、久坂はもう一度笑んで娘の髪をくしゃりと乱す。そうしてゆっくりと立ち上がった。
「待っていろ。各地を一巡りして萩に帰ったら、土産話でもしてやる」
振り向いた久坂の髪がさらりと揺れた。幼い頃を知っているがゆえに、その長さが時の流れを感じさせる。陽射しを受けて佇む久坂は、娘の目にいつになく頼もしい姿を焼き付けた。
「楽しみにしてる」
微かな不安を拭い去り、花が綻ぶように娘が笑う。
その微笑みは、まだ見ぬ地へと旅立つ久坂にとって何よりの餞(はなむけ)となるのだった。










