
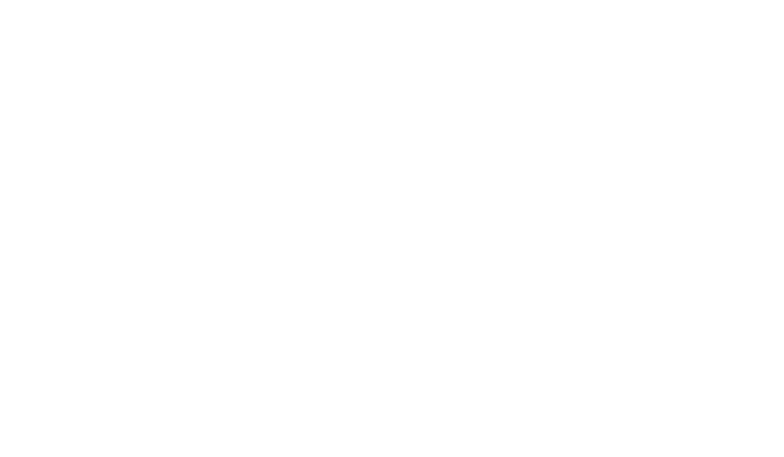
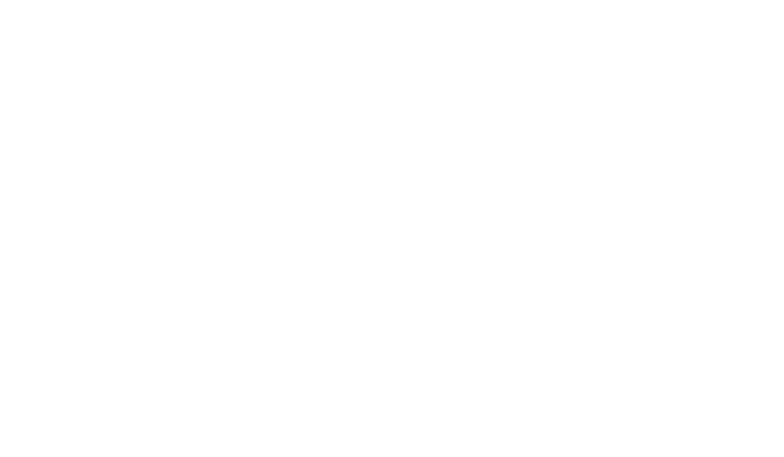
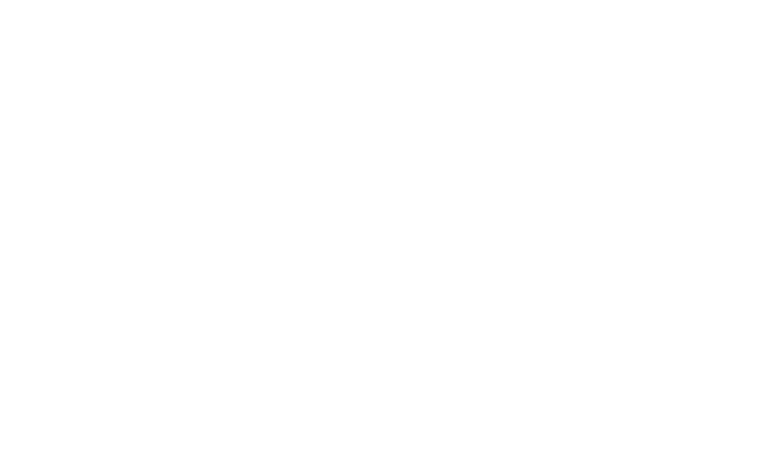
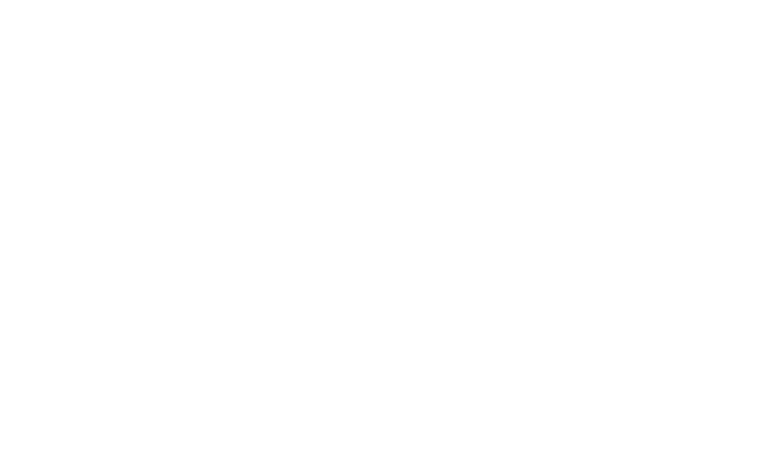
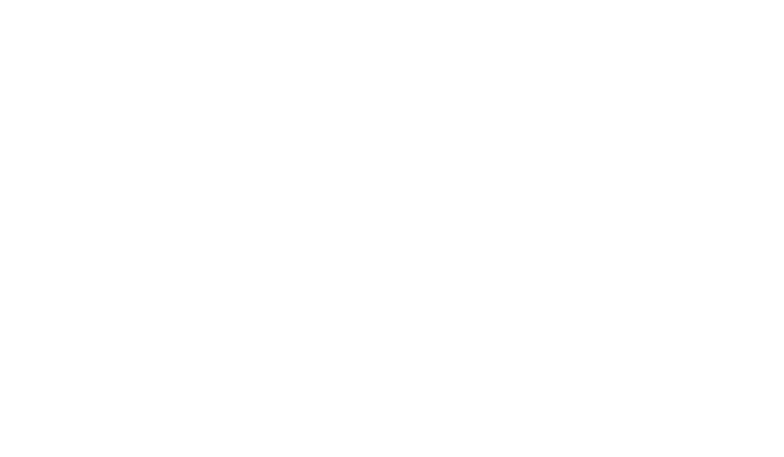
(……うるせぇな)
薄っすらと目を開けば、瑞々しく生い茂った若葉を通して初夏の日差しが降り注ぐ。
その温かさに眠気を誘われてもう一度目を閉じかけたが、今度ははっきりと女の声が聞こえてきた。聞き覚えどころか、昔から嫌と言う程聞き慣れた声だ。
(あいつか……)
盛大にため息をついて寄り掛かっていた木の幹から背を離すと、羽織を片手に身を翻す。古びた神社の境内に、敷石が高杉の体重を受け止める音が響いた。
子供の頃は高いと思っていた大木の枝も、振り返って見上げてみればそれほどでもない。だからこそ、誰にも邪魔されず昼寝をするには持って来いの場所だと気に入っていたのだが――。
「今日は邪魔が入ったな」
そんなことを呟きながらも、足を進める。
境内の外に出てみれば、声の主は予想に違わぬ相手だった。
小奇麗にまとめられた髪と、上物の小紋。誰が見ても位の高い武家の娘だとすぐにわかるだろうが、供も連れずにこんな町外れで一人、しかも自分を取り囲む大の男三人を睨みつけていられるような娘を、高杉は一人しか知らない。長州藩剣術指南役の一人娘。高杉の幼馴染にして許嫁であった。
「謝りなさいっ!」
「なんだと女の分際で生意気な!」
「身の程知らずの小娘が、痛い目を見なければわからないか!」
噛みつくような娘の剣幕に、取り囲む男達の声にも怒気が混じる。
一人の手が刀の柄にのびるのを、高杉は見逃さなかった。素早く足元から適当な小石を拾い上げ、男の足元に投げつける。
「そこまでにしときな」
「なんだお前は。邪魔をするな!」
男達の視線が、突然の闖入者へと向けられる。
「晋作……」
振り向いた娘の瞳が、大きく見開かれていた。
「それはこっちの台詞だっての。人が気持ち良く寝てたってのに、邪魔しやがって。俺は寝起きで機嫌が悪ぃんだ。八つ当たりされたくなけりゃ、とっととそいつを置いて失せな」
「貴様っ、馬鹿にしやがって!名を名乗れっ!」
高杉の言葉に我慢ならなくなったのか、男が一人、抜刀して斬りかかって来る。
「俺が誰かって?」
大して驚きもせず眉を跳ね上げると、高杉はさっと半身を切って男の一撃を難なくかわした。そうしてすれ違い際に、自らの刀の柄で相手の鳩尾を突くことも忘れない。
「うぐっ!」
くぐもった悲鳴を上げて、男がその場に膝を着く。悶絶する男をちらりと一瞥してから、高杉は残った二人へと視線を移した。
「高杉晋作。ここらじゃ、そこそこ通った名だと思うがな」
その一言で、男達の顔色が変わった。
「おい、高杉晋作って言えば確か大組の跡取りだ。手ぇ出したら上の連中に睨まれるぜ!」
「くそっ、行くぞっ!」
悔しそうに顔を歪めながらも、相手が悪いと判断したのか男達はその場を走り去る。
「お、おい、待ってくれ……!」
高杉に打ち倒された男もよろよろと立ち上がると、二人の後を追って姿を消した。
「ったく」
高杉は情けない男達の様子に嘆息すると、立ち竦んだまま一部始終を見つめていた娘へと歩み寄る。
「で、何だってこんな状況になったんだよ?」
「……あの人達が、お父様を侮辱したから」
「侮辱?」
「役立たずの老いぼれは、早く隠居しろって」
「……なるほど」
娘の父親は、何人かいる剣術指南役の中で一番の老齢だ。最近は若い者達が中心になって剣術を教えているため、そのことを揶揄されたのだろう。
「それで食って掛かったってわけだ。あいつらが万一刀抜いてたら、どうするつもりだったんだよ。この棒切れでも拾って応戦するってか?」
娘の足元に落ちている太い木の枝を、高杉は爪先で軽く蹴って見せる。すると娘は、ふいっと視線を逸らした。
(図星かよ)
思っていることをずばりと言い当てられた時、この娘が必ずする仕草だ。高杉はくっと喉を鳴らす。
「あーあ、相変わらず勇ましい限りだな。親孝行な娘を持って親父殿も幸せだろうよ。……けどな」
高杉は急に声音を低めると、娘の細い手首を掴んでぐっと引く。
「あっ」
よろめいた娘の身体が、とんと高杉の胸にぶつかった。娘が顔を上げれば、きつく眉を寄せた高杉と視線がぶつかる。
「お前は女だってことを忘れんな。ガキの頃ならともかく、今はどう頑張ったって、お前じゃあいつらに敵わねえ」
「……ごめんなさい」
しばしの沈黙の後、娘の唇から消え入りそうな声が零れる。
(こいつのことだ。わかってても許せなかったんだろうな)
真っ直ぐな気性は、今も昔も変わらない。一緒に育ってきたからこそ、娘の悔しさも高杉には理解することができた。
「ま、おてんばも程々にしとけってこった。今度また同じような目に遭っても、江戸からじゃ助けに来てやれねえからな」
「えっ」
弾かれたように娘が顔を上げる。
「江戸詰めが決まったの?」
「ああ、番手を命じられた。来月には萩を発つ」
「そう……」
娘は何か言いたそうに口を開きかけたが、結局何も言わずに高杉からそっと離れる。
「助けてくれて、ありがとう」
「……は?」
高杉は目を丸くする。
「こいつは驚いたな。お前の口からそんな言葉が出るとは思わなかったぜ」
「……失礼ね。私だってお礼くらい言うわよ」
「ははっ、そうかよ」
(素直じゃねえな)
思わず噴き出すと、高杉は娘の頭をわしゃわしゃと撫でまわす。
「な、何?くすぐったい……」
「ああ、わりぃ」
高杉は喉の奥でくつくつと笑いながら、手を下ろす。娘は不思議そうに首を傾げた。
「俺が留守にしてる間、あんま無茶すんじゃねえぞ」
ふっと柔らかく目を細めて、高杉は娘を見つめる。するとつられたように、娘の表情も綻んだ。
「……うん。あなたも無茶しないでね」
「わかってるっての」
にっと口端をつり上げて見せる高杉。不敵な笑みは、この男に何よりもよく似合う。
「ほら帰るぞ。送ってやる」
くるりと踵を返す高杉に少し遅れて、娘もまた歩き出す。
そんな二人の後姿を、風に揺れる木々が優しく見守っていた。










