
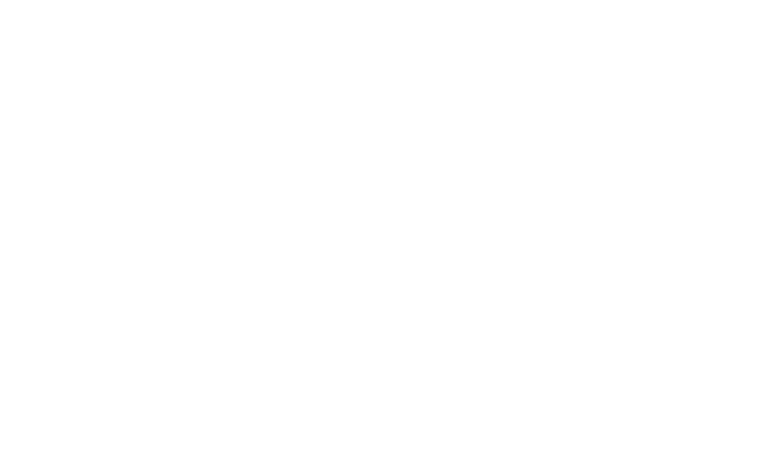
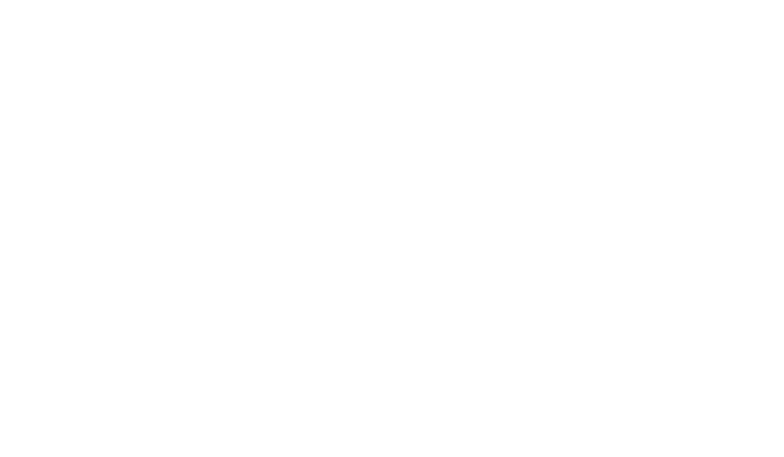
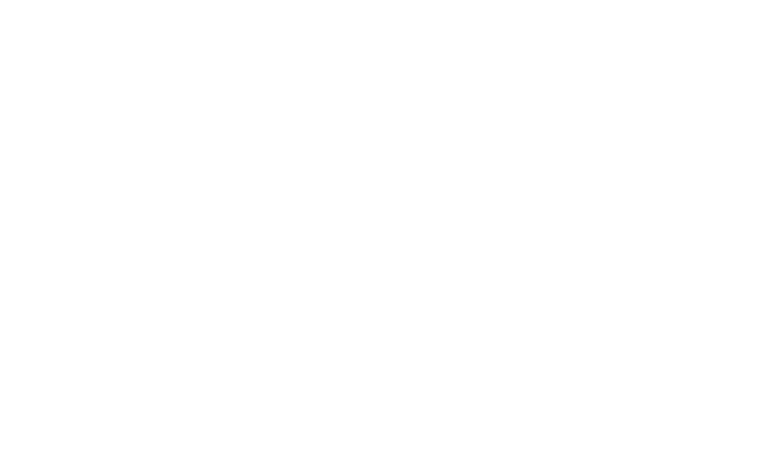
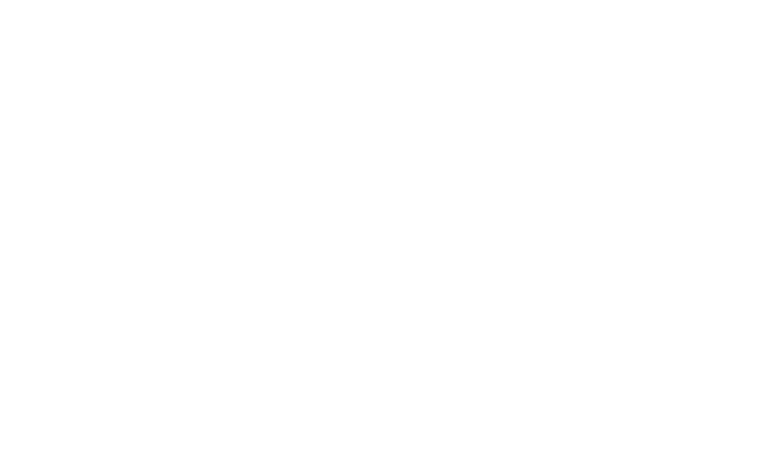
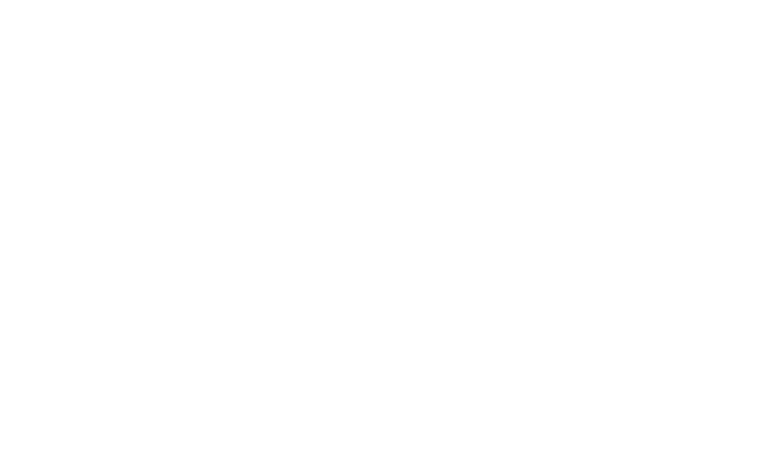
ふと顔を上げれば行燈の火はいつの間にか消えていたが、障子から差し込む光のおかげで部屋の中は書き物をするのに支障がない程度の明るさを保っていた。
(ああ、もう朝ですか……)
あと少しと思って筆を進めるうちに、気づけば夜が明けてしまったらしい。
(この時期は夜が短い)
口元に苦笑を浮かべながら硯に筆を置くと、桂は立ち上がった。静かに障子戸を開くと、柔らかな白い光がその横顔を照らす。桂は眩しそうに目を細めると、冴え冴えしい朝の空気に誘われるように庭へと下りた。
細かい砂利の上を擦る草履が、ぴたりと動きを止める。桂にそうさせたのは、目に飛び込んできた鮮やかな色彩だった。
春を告げる役目を終え、そろそろ散り始めた沈丁花の隣で、牡丹がぷっくりと蕾を膨らませている。たった一輪、しかもまだ開いてすらいないというのに、どこか凛とした風格を漂わせたその姿は、まさに「百花の王」の名に相応しい。
(こんなに大きな蕾をつけるなんて)
鼻先をくすぐった仄かな甘い香りに頬を綻ばせると、桂はそっと蕾に触れた。
(彼女のおかげですね)
早朝からせっせと庭木の手入れをする小さな背中を、今までに何度も目にしている。注がれた愛情を水のように吸収して育ったのならば、この牡丹は遠からず美しい大輪の花を咲かせることだろう。
(楽しみだな)
優しく目を細めながら、触れた時と同じようにそっと蕾から手を離す。
そうして踵を返そうとした時、背後で小さな物音がした。
(……おや)
肩越しに振り向くと、視界の端に小柄な人影が映る。
女中らしい簡素な着物を纏った娘が、柄杓で庭木に水やりをしていた。
(今日も早起きですね)
自然と微笑が零れたが、邪魔をしては悪いと娘に声をかけることはしない。
(ご苦労様)
心の中で呟いて、桂は音もなくその場を離れた。
「――様、桂様」
「……ん?」
微睡みからふと意識を浮上させ、桂はまぶたを開く。柱に寄り掛かったままぐるりと周囲を見渡すと、そこが見慣れた自分の部屋だとわかった。庭の散策から戻った後、居眠りをしていたらしい。
「桂様……?」
(この声……)
障子戸の向こう側から遠慮がちにかけられる声に、ゆっくりと腰を上げる。障子戸を開くと、先程庭で見かけたばかりの娘が桂を見上げていた。
「すみません、ちょっと居眠りしてたみたいで……」
「お休みになられていたのですね。申し訳ございません、朝餉にいらっしゃらなかったもので」
「……朝餉?」
桂ははたと我に返ったように廊下へ出て、空を仰ぐ。既に日は高く、時刻は朝を通り過ぎ、昼に近づいている頃だろう。
「どうやら、僕はずいぶんと寝過ごしてしまったようですね……」
額に手をやっても、出てくるのはため息ではなく苦笑ばかりだ。朝餉を食べ損ねたことで強い空腹感はあったが、午前中に重要な用事がなかったことだけがせめてもの救いだった。
「すみません、僕の分の朝餉が片付かなくて君にもご迷惑をおかけしたでしょう?」
「いえ、そんなことは! それより、もし、よろしければなのですが……」
娘は大きく首を横に振ってみせると、障子戸の陰に隠れていた小さな盆を手に取った。
「昼餉までまだありますから、少し召しあがりませんか?」
おずおずと差し出された盆の上には、香の物を添えた握り飯が二つ、ちょこんと乗せられている。
「僕のために、わざわざ作ってくれたんですか?」
「簡単な物ですが……」
「ありがとう。助かります」
桂が盆を受け取ると、娘はほっとしたように笑顔を見せる。
「では、後ほどお盆を片付けに参りますね」
「ああ、待って」
立ち上がりかけた娘を、桂の声が引き留める。
「僕が食べ終わるまで、ここにいてもらえませんか?」
「え……?」
娘が目を瞬かせる。困惑と言うよりも、純粋に驚いているようだ。
「一人きりの食事というのも、少し寂しいものですから。ああでも、忙しければ断ってくれて大丈夫ですよ」
「あ、いえ。では……」
少しの間の後、娘は再び膝を折って腰を下ろす。
「お邪魔いたします」
「いいえ。こちらこそ無理を言ってすみません」
小さく肩を揺らして自身も座り直すと、桂は握り飯に手を伸ばした。
「いただきます」
「は、はい」
握り飯を口に運ぶ桂をじっと見つめるのも気が咎めたのか、娘は部屋の中に視線を漂わせた。桂の方はと言えば握り飯を食べながら、娘の様子を微笑ましげに見つめている。
「散らかっていてお恥ずかしい。少し返さなければいけない書状を溜め込んでしまいましてね」
「もしかして、昨夜はお休みになられていないのですか?」
「眠る前に朝になってしまっただけですよ。でも、そのおかげで……」
言葉を切って握り飯の最後の一片を口に運ぶと、桂は二つ目の握り飯に手を伸ばす。
「こうして君の作ってくれた美味しい握り飯にありつけている。ふふ、早起きは三文の徳とはよく言ったものです。まあ、いいことは他にももう一つあったんですけどね」
「そうなのですか?」
「ええ」
(君が育ててくれた、あの牡丹の蕾のことですよ)
ふらりと庭を歩くことがなければ、牡丹の蕾に気づくこともなかっただろう。仕事の合間に花が開くまでの日々を指折り数えるささやかな楽しみが増えたのだ。
本音を笑みの内側に隠すと、桂は悪戯っぽく目を細めてみせる。
「近いうちにわかります」
(その時は、君も一緒に)
娘はきょとんとしていたが、桂が心の内でかけた密やかな誘いを知ってか知らずか、やがて花が綻ぶようにふわりと微笑んだ。
「楽しみにしていますね」
「はい。僕もですよ」
柔らかな瞳で頷いて、桂はまた握り飯を頬張る。
他愛もない言葉を重ねる遅い朝餉の時間は、ゆっくりと穏やかに過ぎていくのだった。










