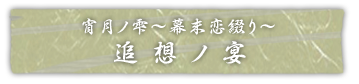万延元年。有備館用掛として江戸の長州藩邸に滞在する桂の元へ、高杉、久坂の二名が訪れてからおよそ一月が経った。季節は春から初夏へ移り変わろうとしている。まだ梅雨には早い江戸の気候は爽やかで、夜ともなれば開け放した障子戸から吹き込む風が心地良い。
そんなある夜のこと、高杉と久坂は桂の部屋に集まっていた。二人が江戸に下った目的である幕府の軍艦教授所への入所が無事決まったことを祝い、桂が酒宴の席を用意したのだ。
酒宴とは言っても芸妓を呼ぶわけでもなく、豪勢な料理があるわけでもなく、ただ桂が用意した上物の酒を酌み交わすというごくささやかなものだ。
藩内でもそれなりの地位にある桂にしてみれば、気の利いた料亭に二人を連れて行き好きに飲み食いさせてやることも十分にできたが、そこはまだ年若い二人のこと。酒に酔って羽目を外しすぎるようなことがあれば、せっかく決まった入所が取り消しになるかもしれない。
万が一にもそんなことにならないようにと、年長者として、そしてかつて同じ人物――今は亡き吉田松陰を師と仰いだ者としての気遣いであった。
「一年ぶりの江戸はいかがです?」
空になった久坂の盃に酒を注ぎながら、桂は口を開く。
「たった一年ですが、俺が滞在していた頃とは明らかに違う空気を感じます。桜田門外で井伊直弼が暗殺されてからというもの、幕府に反感を持つ者たちの動きが活発になっている……。彼らに後れを取らぬようにするためにはどうすればいいのかと、日々考えるばかりです」
桂は気軽な世間話のつもりであったが、ここで世情に対する持論を展開してしまうのがいかにも真面目な久坂らしい。
「高杉君はいかがですか?」
桂が徳利を傾けると、高杉は残っていた酒を一息に飲み干し盃を差し出した。
「空気の違いなら俺も感じますよ。やっぱり江戸の方が賑やかだ。萩の田舎より退屈しなくていい。おかげで毎日色んな刺激をもらって楽しい限りです」
桂が酒を注いでやると、久坂とは対照的な答えが返ってくる。これもまた、奔放な高杉らしい答えであった。
「……刺激? お前が受けているのは真っ当なものではないだろう」
「あん? どういう意味だ」
「いい加減に吉原を冷やかして回るのは止めておけと言っているんだ。俺たちは学ぶためにここにいる。色ごとにかまけている暇などないだろう」
「別に冷やかしじゃないぜ? 下見だ下見。江戸の吉原や京の島原は密談にうってつけだって桂さんも言ってだろ。そうですよね? 桂さん」
「ええ……まあ、確かに言った気がしますが……」
何も毎日欠かさず足を運べと言った覚えはないと、桂は苦笑を浮かべる。
「ほらな。俺は今のうちから馴染みの店をつくって、先のことに備えてんだよ」
「ふん、どうだかな」
得意顔の高杉と、呆れ顔の久坂。二人を前に桂はますます苦笑を深めたが、その複雑な心境をよそに、二人の嫌味の応酬は続く。
「つーか、久坂。お前もいい加減、女の扱いくらい覚えねえといざって時に恥かくぜ?」
「なっ……!?」
久坂の動揺を表すように、手元の盃から酒が零れ落ちた。
「お、お前になど言われなくとも、俺だって……!」
「ほーお。じゃあお前、接吻の一つもしたことあるのかよ? それとも何か? そんな顔して、もうそれ以上先も試してみたか?」
「っ……げほげほごほっ!」
今度は思い切りむせたことによって、久坂の盃から再び盛大に酒が零れた。その横顔が耳まで紅潮しているのは、酔いが回ったせいではないだろう。高杉は勝ち誇ったような笑みを浮かべる。
「ほーらな、強がりやがって俺の言う通りじゃねぇか。仕方ねぇから今度お前にもいい店紹介してやるよ」
「断るっ! 願い下げだ!」
「照れんなよ。ったく、この朴念仁め」
「っ……貴様……! さっきから黙って聞いていれば、桂さんの前で下世話な話ばかりつらつらと、いい加減にしろよ……!」
久坂の手が、右脇に置いていた刀にかかる。
「お? なんだよ、やるのか?」
高杉は、すかさず自分の刀に手をのばした。
「いいぜ? そっちがその気なら、久々に相手してやろうじゃねーか!」
「望むところだっ!」
売り言葉に買い言葉。二人が勢いよく立ち上がった時だった。
「高杉君、久坂君!」
桂が声を張った。
「それくらいに。僕の部屋で暴れないでくださいね?」
桂はにっこりと微笑んでいる。だがその笑顔の奥から漂うただならぬ黒い気配と威圧感に、高杉と久坂は顔を見合わせた。
「じょ……冗談ですよ、桂さん! 本気でやり合ったりしませんって! なあ、久坂?」
「あ、ああ、そうだな。大変失礼いたしました」
「そうですか、それは良かった。ではお座りなさい」
桂が促すと、二人はすぐさま腰を下ろし刀を置いた。
「いい子ですね、二人とも。お酒は楽しく飲まなくては。さあ、どうぞ」
恐縮しているのか、恐怖しているのか、はたまたその両方なのか。やけに縮こまる二人に、桂はなみなみと酒を注いでやる。
「まったく、君たちはあの頃から変わりませんね。まだ松陰先生がご健在だった頃から、暇さえあればぶつかり合って……」
「お言葉ですが、桂さん。いつもくだらないことで俺に喧嘩を吹っかけてきたのは高杉の方です」
「はあ!? お前、人のせいにしてんじゃねーよ!」
「俺は事実を言っているだけだ」
「んだと!?」
言っている傍から再び言い争いを始めた高杉と久坂に、桂はやれやれと肩を竦める。もう一度止めるのは面倒だと諦めて、しばらく放っておくことにする。
そうしているうちに桂の脳裏には、懐かしい光景が蘇ってきた。
――時を遡ること、数年前。
萩の松本村にある杉家の敷地内に、松下村塾という私塾があった。元は玉木文之進によって開かれたその私塾の名を継いだのは、甥の吉田松陰である。かつて浦賀に現れたペルリの黒船に密航し、異国へと渡ろうとしたことで投獄されたという特殊な経験を持つ男だ。だがその人柄や豊富な知識に惹かれ、松下村塾の門を叩く若者は後を絶たない。
高杉と久坂もそんな好奇心旺盛な塾生の一人であった。
「――では今の故事について、どう思いますか? 高杉君」
古びた本を手に、松陰が問う。八畳ほどの小さな学び舎には、松陰の他、塾生の高杉と久坂がいた。
「俺は愚かだと思います。ここぞと言う時にすぐに動かないなんて、ただの腰抜けがすることだ。俺なら考えるより先にまず行動を起こします。後悔するのはそれからでいい」
「久坂君はいかがですか?」
「俺は考えなしに行動する方がよほど愚かだと思います。ただ闇雲に動いて犬死にするなどなんの意味もない。まずは慎重に相手の出方を伺うべきです」
「なるほど、どちらの意見も実に興味深いですね」
「お言葉ですが、松陰先生」
「なんですか? 久坂君」
「高杉は間違っています。戦において、将の判断は絶対。それ故に一つ間違えれば、兵を無駄に死なせることになります。高杉のやり方では、誰も納得しないでしょう」
「じゃあお前は、臆病風吹かせていつまでも隠れてろって言うのか? それこそ兵の士気がガタ落ちだろうが」
「戦術における優秀な将とは、いかに自軍の被害を少なく留めるかだ。戦国乱世でもなければ、お前のような考えは通用しない」
「何を根拠に言ってやがる!」
「根拠など必要あるものか。俺は正論を言っているだけだ」
徐々に熱を帯びる高杉と久坂の論戦を、松陰はただ静かに見守っている。この二人だけでなく、松下村塾の塾生たちは時に激しく論戦を繰り広げたが、松陰はあえて止めたり、口を出したりすることはなかった。その激論の末にしか見えないものがあると知っているからだ。
「なんだか賑やかですね」
「桂君ではないですか。ずいぶんと久しぶりですね」
杉家の庭の方から桂が顔を見せると、高杉と久坂もそちらを振り向いた。
「ご無沙汰しております、松陰先生。高杉君と久坂君もお元気そうで何よりです」
桂はその場で一礼すると、塾舎の縁側に腰を下ろした。
「いつ萩に戻って来たのですか?」
「昨日ですよ。早く顔を出そうと思っていたのですが、色々とやることが多くてすっかり遅くなってしまいました。まあその代わり、こうしておみやげを用意することができましたが」
桂はそう言って、抱えていた包みを差し出す。
「どうぞ。萩城下に出来たばかりの団子屋で買ってまいりました。町娘たちの間で、美味しいと評判だそうですよ」
桂が包みを開くと、そこには白と薄紅の串団子があった。つやつやとした丸い見た目は、町娘たちの噂通りいかにも美味しそうで食欲をそそる。
「これは、わざわざありがとうございます。ではせっかくですから、少し休憩にして皆でいただきましょう」
「松陰先生、俺が茶を淹れてまいります」
「おや、そうですか? ではお願いします」
「はい、お任せください!」
久坂は足早に台所へと向かった。
「……もしかして久坂君、甘いものお好きでした?」
桂の目には、久坂の足取りがどこか弾んでいるように見えたようだ。
「ああ、確かそんなことを高杉君から聞いたような……」
「もしかしなくても大好きですよ、あいつ。本人はあれで隠してるつもりですけど、全然隠せてないっつーか。指摘したら指摘したで『男子たるもの甘いものなど食わんっ!』とか言い出しそうですけど」
「別に男子が甘いものを好んではいけないということもないと、私は思うのですがね。……ですがまあ、言わないでおきましょう。きっと拗ねてしまいますからね、久坂君は」
「ふふっ、わかりました。では僕も知らないふりをしておきます」
「ええ、そうしてあげてください」
自身の不在中にそんな話をされているとはつゆ知らず、そこに人数分の茶を淹れた久坂が戻って来た。
「……何かありましたか?」
なぜか松陰と桂から微笑まし気な眼差しを向けられていることに気づいて、久坂は眉を寄せる。
「いいえ、僕は何も」
「それより、さあ久坂君も座りなさい。お団子をいただきましょう」
「? はあ……」
いまいち腑に落ちないといった顔の久坂を見て、高杉は必死に笑いを堪えていた。
「江戸の様子はいがかでしたか?」
団子をかじりながら、松陰は問う。
「開国以来の不安定な情勢は相変わらずですが、最近は幕府内にも一部不穏な動きがあるようですよ。攘夷寄りの者との間に摩擦が起きているとか、いないとか……」
「……なるほど、幕府も一枚岩というわけではないのですね」
「ええ。いずれにせよ、我が藩としては今はまだ静観すべき時のようです」
「……やはり見識を広げるためにも、一度は江戸に足を運ばねばなりませんね。桂さんのお話を聞いていると、まだまだ俺の視野は狭いのだと思い知らされます」
「おや、久坂君の江戸遊学はまだでしたか?」
「はい。久坂家は一応藩医の家柄ですから、望んでもなかなかお許しが出ないのです」
「……そうでしたね。高杉君は確か、一度下ったことがあると聞きましたが?」
「あー……確かに、三、四年前に一度だけ。けど、とくになんの思い出もないですね」
「……ふん、お前のことだ。どうせ遊び呆けていただけだろう。まったく、しょうもない」
「……んだと?」
咥えていた団子の串をぺっと吐き出して、高杉は隣に座る久坂を睨む。
「俺は思ったことを正直に言っただけだが? せっかく与えられた勉学の機会を無駄にするとは、嘆かわしい限りだな」
「この野郎……松陰先生と桂さんの前だからって、いい格好しやがって。そんなに褒められたいかよ朴念仁!」
「誰が朴念仁だ!? このあずき餅めっ!」
「あずき餅って言うんじゃねぇっ! 図体だけでっかい木偶の坊がっ!」
「なんだと!? いいだろう、木偶の坊かどうか確かめさせてやる!」
「望むところだ、表に出やがれっ!」
高杉と久坂は、同時に刀を取って立ち上がった。
「二人とも落ち着きなさい。松陰先生の前ですよ」
「構いませんよ、桂君」
止めに入ろうとする桂を、松陰は静かに制した。
「たまには、とことんぶつかり合ってみるのも必要でしょう。学問でも武道でもそれは同じことです。……ですが、万一のことがあってはいけませんから、やるならそこの物置にある木刀を使ってくださいね」
どうやら松陰に二人を止める気は一切無いらしい。それを察すると、桂は立ち上がろうと浮かしかけた腰を再び縁側に下ろすのだった。
松陰の言いつけを守って木刀を手にした高杉と久坂は、庭に出るとすぐさま打ち合いを始めた。
「うおらっ!」
先に動いたのは高杉だ。暴れ牛と揶揄される性格をそのまま体現したかのような、直線的な踏み込み。その気迫を真正面から受けたのが並大抵の者ならば、それだけで怖気づいてしまうだろう。だが、久坂は冷静だった。
「ふん、突っ込めばいいというわけでもなかろうっ!」
正中線を僅かに逸らして高杉の一撃をかわすと、即座に反撃に出る。その長身から振り下ろされる木刀は、ぶんっと鋭い音を放った。
「へっ、よく言うぜ! 型通りの道場剣術で何ができるって言うんだよ!」
「っ!?」
身を低く屈めた高杉が中途半端な位置から繰り出した斬撃に、久坂の反応が遅れた。
「ほーらな! お行儀良くしてるだけじゃ、俺には勝てねーぞっ!」
「貴様っ……!」
打っては打たれ、打たれては打ち返し、二人の戦いは徐々に激しさを増す。それは初めの内こそ剣術の模擬試合とかろうじて呼べるものだったが、時が経つにつれ、ただの喧嘩のようになってくる。
「……松陰先生、いつまでやらせておくんですか?」
ため息混じりに、桂は松陰を振り返る。
「うーん、そうですね。少しやれば気が済むと思っていたのですが、困りましたね」
畳の上に座した松陰は、言葉とは裏腹にのほほんと子供の喧嘩じみた打ち合いを見つめている。
「止めないんですか?」
「残念ながら、止められないのですよ私には。君も知っての通り、私には武の才能がありませんから、止めるにしても加減がわからないのです。下手に手を出すと、かえってあの二人を危ない目に遭わせてしまいそうでして……」
「やれやれ……」
桂は苦笑して、湯呑を縁側に置いた。
「それでは僕が代わりに」
そう言って立ち上がり、打ち合いを続ける二人の元に歩み寄る。
「高杉君、久坂君。二人とも、もうその辺りにしておきなさい」
「止めないでください桂さん! 今日こそこいつの無駄に高い鼻っ柱をへし折ってやらねぇと、気が済まないんですっ!」
「貴様こそ覚悟しろ! いつもいつも俺をおちょくりおって……今日という今日こそ許さん!」
桂の仲裁を無視して、二人は睨み合う。
「……はあ」
それはそれは深いため息をついた直後、桂は動いた。
「うおっ!?」
「くっ……!?」
足払いをかけられた高杉の体が宙に浮き上がり、背中側から軽い一打を当てられた久坂が前につんのめる。二人はほぼ同時に、その場に倒れ込んだ。
「……まったく、君たちは」
目にも止まらぬ早業で二人を薙ぎ倒した桂は、二人の手にしていた木刀も奪い取っていた。その切っ先が、まだ倒れたままのそれぞれの首筋に突きつけられる。
「二人とも口だけは立派ですが、全く鍛錬が足りませんね。第三者に隙を突かれた上、こんなにも簡単に得物を奪われるとは……。これが本物の斬り合いだったら、君たち僕に首を跳ねられてとっくに死んでますよ?」
桂は眼下にいる二人へと、交互に冷めた眼差しを送った。
「高杉君。力が有り余っているのは元気で結構ですが、無駄な力が入り過ぎて太刀筋がぶれています。それでは敵に当たらない」
「は、はい……」
「逆に久坂君。型は綺麗ですが慎重になりすぎて気勢が全く感じられません。それでは虫一匹斬れませんよ」
「き、肝に銘じます……」
「これ以上やると言うなら、僕が直接稽古をつけて差し上げます。ただし、五体満足は保証できませんが……どうしますか?」
地に伏したまま、高杉と久坂は視線を交えた。たった今、激しい打ち合いを繰り広げた相手とはいえ、感じた身の危険は同じだった。
「申し訳ありませんでした……」
明らかに意気消沈した二人の声が重なる。
「そうですか、物わかりのいい子たちですね」
桂はにっこりと微笑むと、その場に木刀を置いて縁側に戻った。
「ふふ、お見事です桂君。神道無念流免許皆伝の剣豪は伊達ではありませんね」
「よしてください、松陰先生。今のは剣術でもなんでもありませんよ。……ねえ、お二人とも?」
ようやく立ち上がった高杉と久坂は、桂が笑顔を向けても顔をひきつらせたままだ。その様子に松陰はふっと微笑む。
「二人とも泥だらけになってしまいましたね。そろそろ妹たちが湯を沸かしている頃です。二人で風呂にでも浸かって、汚れを落として来なさい」
「……わかりました」
「お借りいたします……」
「……行こうぜ」
「ああ……」
高杉と久坂はなんとも微妙な顔をしながらも、連れ立って風呂場の方へと去っていく。
「……また喧嘩にならなければいいですね」
「お互いの背でも流し合えば、仲直りもできるのではないですか?」
それはそれで、また喧嘩の火種になりそうな気がしないでもない。桂はそう思ったが、口には出さずにいた。松陰もわかって言っているのだろう。わかりにくいがこれも松陰なりの冗談なのだ。
ならば何も言うまいと、桂は縁側に置いてあった二冊の帳面を手に取る。
「……どう思いますか?」
ぱらぱらと帳面をめくっていると、松陰が桂の隣に腰を下ろした。
「さすがは松陰先生の秘蔵っ子ですね」
帳面から視線を上げ、桂は目を細めた。桂が手にしている帳面は、高杉と久坂がそれぞれ松陰の講義を受ける際にいつも使っているものだ。どちらにも講義の内容はもちろん、発展させた様々な持論が隅々までびっしりと書き込まれている。そこから二人の飛び抜けた才能の片鱗が見て取れた。
「今はまだ、若さゆえの粗ばかりが目立ちますが、この先の彼らの成長を思うと恐ろしいものがありますね」
「君の目にもそう映りますか?」
「ええ。あなたに先に師事した先輩としては、うかうかしていられませんね。松陰先生」
そう言って笑った桂につられるように、松陰も頬を綻ばせる。
「心こそ、心迷わす、心なれ、心に心、心ゆるすな」
「……沢庵禅師のお言葉ですね」
「ふふ、さすがは桂君。ご存知でしたか」
「その一説は有名ですから」
「喜びも悲しみも怒りも憎しみも、全て己の心からくるものです。それに振り回されて己を見失わないよう、常に己を律せるようにならねばなりません。それができるようになった時、彼らは真の成長を果たすのかもしれませんね」
松陰はこの上なく、優しい微笑を浮かべていた。その温かな眼差しを感じると、桂の胸にも温かいものが滲みだす。
「あの二人の将来が楽しみですね」
「ええ本当に楽しみです。桂君、いずれ彼らを江戸にやろうと思っています。私はここから動くことができませんが、その時は彼らをよろしくお願いします。どうか見守ってあげてください」
「ええ、任せてください」
――そこでふと、桂は我に返った。
「……おっと!」
その気配を感じて咄嗟に徳利を避けると、直後に高杉と久坂が畳に倒れ込んでくる。
「久坂ぁ……みろ……やっぱ……俺の方が……強いじゃ……ねぇか……」
「何をぉ……? 俺……とて……まだまだ……飲める……」
「上……等だ。なら……今度……は……ぐうぅうううー……」
「おい……寝るな……高杉……俺は……ま……だ……すうぅうううう……」
「…………」
言葉の途中で、高杉と久坂はほぼ同時に眠りについた。
「……やれやれ、またですか」
徳利を置いて、桂は今夜何度目になるかもわからないため息をつく。どうやら桂が懐かしい思い出に浸っている間に、二人は好きなように酒を飲んですっかり酔っぱらってしまったらしい。
徳利の中はもう空になっている。酒をほとんど飲まれたことについて、桂は二人を咎めようとは思っていなかった。そもそも飲まれて困る酒ならば、最初から二人を誘ったりはしない。問題なのはこの後だ。
「酒は飲んでも飲まれるな。……いい加減に学んでほしいな。君たち、重いんですよ」
藩邸の中でも桂の部屋は比較的広い方だが、それでも大の男が二人も寝そべっていたら、今夜桂の眠る場所はない。桂は仕方なく、高杉と久坂を背負ってそれぞれの部屋へと運ぶことにした。
「……ふう」
酔っ払い二人をそれぞれの部屋に適当に放り込むと、桂は縁側に立って一息ついた。重労働の後に肌に感じる夜風は実に心地が良い。
その時ふと、足元が明るくなった。見上げれば琥珀色の大きな月が桂を照らしている。その優しく柔らかな光は、どこか記憶の中の松陰を彷彿とさせた。
「……今度はあなたがそこから見守っていてくださいね、松陰先生」
月に向かって微笑みかけると、桂も自分の部屋へと戻る
後はただ、穏やかな月明かりが揺れるばかりだった。